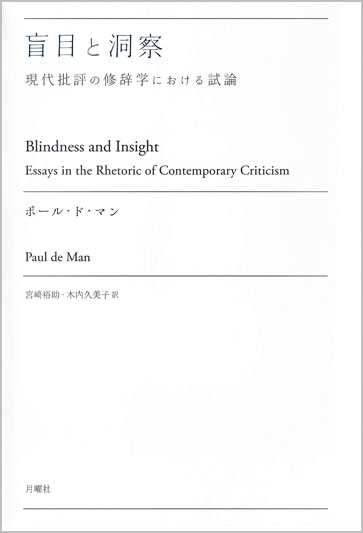 ポール・ド・マン 著
ポール・ド・マン 著宮﨑裕助+木内久美子 訳
盲目と洞察
現代批評の修辞学における試論
月曜社
46判・上製360頁
本体価格 3400円
ISBN 978-4-901477-98-7
2012年9月20日発行
⇒出版社紹介ページ
【本書の紹介文】
テクストと向きあう〈読むこと〉の透徹した営みによって、
現代における批評の新たな方向性を決定づけた古典。
ブランショ、プーレ、デリダらと果敢に対峙し、
不可避的な内的齟齬への盲目性によって
彼らの洞察そのものが支えられていることを暴く。
鋭利な考察が今なお輝きを放つ、イェール学派の領袖の主著。
1971年初版本よりの完訳。
【訳者より】
本書は、20世紀文芸批評の極点のひとつをなす文学者、
ポール・ド・マンの代表作であり、訳書が長らく待望されてきましたが、
このたび原著刊行後40年を経てついに訳書を上梓することができました。
原文の難解さに引きずられないよう、訳文をできるかぎり工夫し、
訳註も充実させました。
文学や批評、芸術、思想に興味をもつすべての方におすすめです。
どうぞよろしくお願いします。(宮﨑 裕助)
以下、2012年11月20日追記──────────
早くも以下の書評を頂戴しました。この場を借りてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。
■ 土田知則氏(千葉大学)『図書新聞』2012年11月17日号(第3086号)。
──「まさに待望の翻訳[...]。本書の邦訳により、日本におけるド・マン研究はようやく新たな端緒を迎えたと言えるだろう。」
■ 山城むつみ氏(批評家)『週刊読書人』2012年11月9日号(第2964号)。
──「[...]読むことの極北へとひとり進んだド・マンが五十二歳で出したこの第一評論集が四十一年の歳月を経て今、回帰して来たことは、個人的に、耐え難く重い一撃である。」
追記ここまで───────────────
著者:ポール・ド・マン(Paul de Man)
1919年ベルギー・アントワープ生まれ。ブリュッセル自由大学で工学、後に化学を専攻し、哲学や文学も広く学ぶ。1948年合衆国に移住。1960年ハーヴァード大学にてPh.D. 取得(比較文学)。コーネル大学、ジョンズ・ホプキンズ大学、チューリッヒ大学などで教鞭を執り、1970年以降、イェール大学比較文学科教授。1983年没。著書に、本書『盲目と洞察』(1971年、第二版1983年)のほか、『読むことのアレゴリー』(1979年;岩波書店、2012年)、『ロマン主義のレトリック』(1984年;法政大学出版局、1998年)、『理論への抵抗』(1986年;国文社、1992年)、『戦時評論集 1934-1943年』(1988年)、『批評著作集 1953-1978年』(1989年)、『ロマン主義と現代批評』(1993年)、『美学イデオロギー』(1996年;平凡社、2005年)、『ポスト・ロマン主義の窮状』(2012年)。
以下は「目次」「原著(初版)の紹介文」です。
【目次】
まえがき
第Ⅰ章 批評と危機
第Ⅱ章 アメリカのニュークリティシズムにおける形式と意図
第Ⅲ章 ルートヴィヒ・ビンスヴァンガーと自己の昇華
第Ⅳ章 ジェルジ・ルカーチの『小説の理論』
第Ⅴ章 モーリス・ブランショの批評における非人称性
第Ⅵ章 起源としての文学的自己──ジョルジュ・プーレの著作について
第Ⅶ章 盲目性の修辞学──ジャック・デリダのルソー読解
第Ⅷ章 文学史と文学のモダニティ
第Ⅸ章 抒情詩とモダニティ
訳者あとがき
索引
【原著書誌】Paul de Man, Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, Oxford University Press, 1971.
【原著(初版)の紹介文】(初版ソデ部分に付された文章の日本語訳)
アメリカとヨーロッパにおける今日の文学研究は、主題論(テマティスム)的批評、構造主義批評、現象学的批評のあいだの緊張によって形づくられていると主張されることがよくある。少し前までは、批評の手法は、歴史批評、形式主義(フォルマリズム)批評、実存主義批評のいずれかだと言われていた。本書に収められた九つの章において、ド・マン教授が主張するのは、そのようなレッテルが歴史的な分類には役立つとはいえ、文学研究に適用されるやしばしば誤解を招くものとなってしまうということである。つまり、最良の批評的洞察はおよそ体系的でないことが常なのであって、学派や運動を強調することは「もっとも優れた貢献にそなわる個別性を抹消してしまいがち」なのである。ド・マン教授によるこの第一論集が集中的に論じているのは、国籍や方法がなんであれ、あらゆる批評家のうちにくり返し生ずるパターンであり、彼はこれらのパターンを、批評理論と批評的実践とのあいだに存するもろもろの齟齬のうちに探求するのである。
本書で論じられるヨーロッパの書き手たちは、スイスの精神科医にして哲学者ルートヴィヒ・ビンスヴァンガー、ハンガリーのマルクス主義批評家ジェルジ・ルカーチ、複雑難解をもってなる二人のフランスの批評家、モーリス・ブランショとジョルジュ・プーレ、そして異彩を放つ影響力のあるフランスの書き手ジャック・デリダである。とりわけ本書が詳細な分析を施しているのが、このデリダのルソー註釈である。ド・マン教授は、こうした書き手たちの高度に個別的な「行程」──彼らの批評的言説の論理と修辞と、彼らが解釈するテクストの論理と修辞とのあいだの相互作用──を跡づけることで、誤謬と真理、盲目と洞察からなる隠された根底的な布置を暴き出すことができるのであり、そしてこの布置は、文学研究総体に適用されるものなのである。
ド・マン教授は、フランスの構造主義、アメリカのニュークリティシズムといった諸潮流がもつ意義をも探究している。最後の二つの章において彼が追究しているのは、文学史と文学のモダニティをめぐる広汎な問いであり、その徹底した議論の射程は、そこで検討されている個々の作家よりもはるか遠くに及んでいる。それは、高度に熟達した力量をそなえた一個の解釈的な批評作品として、文芸批評の個々の対象を超えて、いっそう広大な問い、文学研究が絶えず立ち戻らねばならない問いへと通じているのである。すなわち、自己についての問い、構造と意図の問い、比喩形象と表象的で再現的な語法の問い、そして文学言語についての問いである。