去る3月2日(土)、新潟大学駅南キャンパスにて国際シンポジウム「Über die Identität(同一性を超えて)」が開催されました。今回は、ドイツ観念論研究の碩学、マンフレート・フランク氏(テュービンゲン大学)、クリストフ・ヤメ(リューネブルク大学)氏をお迎えし、企画者の栗原隆氏(新潟大学)を加えて三名の方々から、それぞれ下記の論題でご報告をいただきました。また、特定質問者として久保陽一(駒澤大学)、大河内泰樹(一橋大学)、竹峰義和(東京大学)の各氏を、通訳として満井裕子氏(実践女子大学)をお迎えしました。当日は人文学部の教員をはじめ、ドイツ哲学や文化に関心をもつ学生や、学外の方々にもお集まりいただきました。皆様ご来場ありがとうございました。
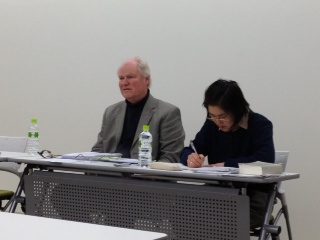
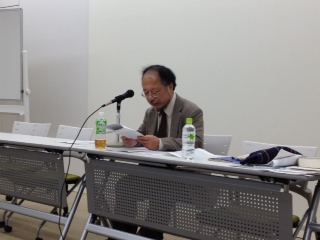
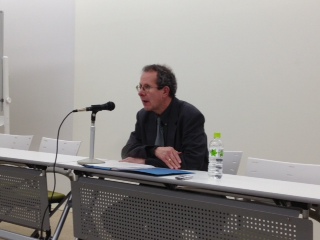

論題(発表順)
■マンフレート・フランク「同一性と非同一性の同一性──『絶対的同一性体系』へと至るシェリングの道程」
■栗原 隆「連続性と同一性──シェリングの同一哲学に対する剽窃疑惑をめぐって」
■クリストフ・ヤメ「想像にとっての真理──若きヘーゲルとヘルダー」
フランク氏、ヤメ氏のドイツ語原稿(※前者のみ邦訳あり)は、日本ヘーゲル学会HP(http://hegel.jp/)からダウンロード可能です(2013年3月現在)。ヤメ氏については、ドイツ語原稿から原典引用部分を中心に訳出したレジュメがありますので、こちら[→PDF]からご覧ください。
以下に各氏による報告の概要を記しました。
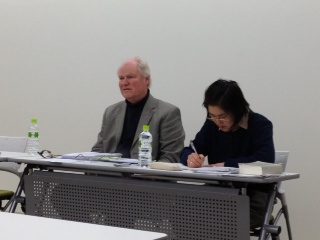
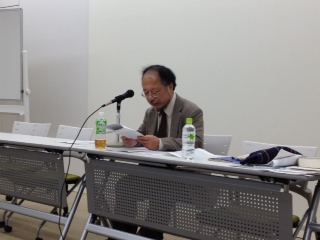
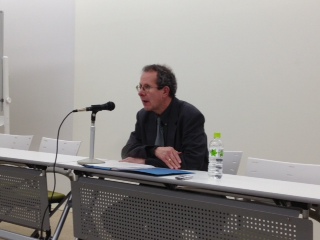

論題(発表順)
■マンフレート・フランク「同一性と非同一性の同一性──『絶対的同一性体系』へと至るシェリングの道程」
■栗原 隆「連続性と同一性──シェリングの同一哲学に対する剽窃疑惑をめぐって」
■クリストフ・ヤメ「想像にとっての真理──若きヘーゲルとヘルダー」
フランク氏、ヤメ氏のドイツ語原稿(※前者のみ邦訳あり)は、日本ヘーゲル学会HP(http://hegel.jp/)からダウンロード可能です(2013年3月現在)。ヤメ氏については、ドイツ語原稿から原典引用部分を中心に訳出したレジュメがありますので、こちら[→PDF]からご覧ください。
以下に各氏による報告の概要を記しました。
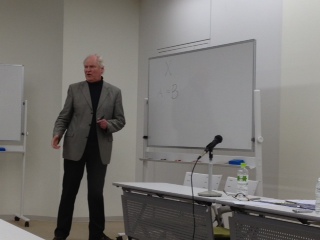 フランク氏が主題に掲げた「同一性と非同一性の同一性」は、『差異論文』におけるヘーゲルの表現で、友人シェリングが当時提唱していた「絶対的同一性の体系」の核心を定式化したものである。ヘーゲルの理解は直ちにシェリング自身によっても「我が意を得た」とばかりに支持された。フランク氏の報告は、同一性概念に関して二人が互いに同調しあった(ように見える)この瞬間に微かな不協和音を認め、その必然性を、初期~後期シェリングの同一性理解の背景・生成・意義といった広い文脈から跡づけるものである。
フランク氏が主題に掲げた「同一性と非同一性の同一性」は、『差異論文』におけるヘーゲルの表現で、友人シェリングが当時提唱していた「絶対的同一性の体系」の核心を定式化したものである。ヘーゲルの理解は直ちにシェリング自身によっても「我が意を得た」とばかりに支持された。フランク氏の報告は、同一性概念に関して二人が互いに同調しあった(ように見える)この瞬間に微かな不協和音を認め、その必然性を、初期~後期シェリングの同一性理解の背景・生成・意義といった広い文脈から跡づけるものである。上の定式により〈二重化された同一性X〉は、同一律や矛盾律といった通常の論理法則を越えた内包をもち、存在論や判断形式をめぐるシェリングの洞察の文脈から解き明かされなければならない。それに関してフランク氏が取りあげた論点はきわめて多彩かつ重層的である(1.ライプニッツの「不可識別者同一の原理」をめぐる近代の論争史(ヒューム、カント)との連続性、2.『ティマイオス』と『ピレボス』、カントのExistenz概念、プルーケ論理学の受容、3.現代の心身問題との親和性、4.中期・後期の判断論におけるコプラの解釈(Bandやals)など)。
ヘーゲルの場合Xは絶対的精神であり、つまり、たえず働く自己知の発展的運動のなかに他者(自然)を本質的契機として無限に内化してゆく「存在者の存在」(óntos ón)である。それに対しシェリングの場合は、そうした精神による他者との反復的結びつきでさえ絶対的同一性の単なる一契機としか見なさない。Xはむしろ、精神とその他者(自然)といった関係項を結ぶ「絆」として理解される。それは反省による判断形式では直接捉えがたいコプラの不定形Seinであり、ヘーゲルの想定する具体化された存在に比べ、よりプリミティブな、しかし可能性を豊かにそなえた存在である。
フランク氏によれば、シェリングによるこうした存在理解のモチーフは、後期の現実存在の哲学に全面的に依らずとも、同一哲学期の著作や講義のうちに萌芽的に見出すことが可能である。シェリングはそれゆえ、自らの「同一性」に関して『差異論文』のヘーゲルが提供した解釈上の手助けを――その直後の同調とは裏腹に――本質的にはおよそ「最後まで拒んだ」ことになる。
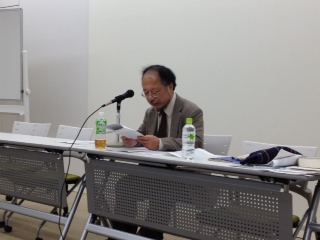 栗原氏は、1800年前後にラインホルトとシェリングを中心にバルディリやヘーゲルを巻き込んで繰り広げられた「同一性の正統性」をめぐる論争の詳しい経緯から、シェリングの同一性概念の限界、そしてヘーゲルが自己関係性・無限性モデルの同一性に軸足を移動したことの必然性を跡づけた。栗原氏が数多くの一次文献を用いて鮮明に描いた論争の経緯を、ごく簡略化して言うと次のようになる。
栗原氏は、1800年前後にラインホルトとシェリングを中心にバルディリやヘーゲルを巻き込んで繰り広げられた「同一性の正統性」をめぐる論争の詳しい経緯から、シェリングの同一性概念の限界、そしてヘーゲルが自己関係性・無限性モデルの同一性に軸足を移動したことの必然性を跡づけた。栗原氏が数多くの一次文献を用いて鮮明に描いた論争の経緯を、ごく簡略化して言うと次のようになる。ラインホルト(『一般文芸新聞』)は、シェリングの『超越論的観念論の体系』が主観的・客観的観念論の同一性を探究しようと企てながら両者の対置までしか到達していないと指摘し、バルディリ(『第一論理学綱要』)のような論理的実在論にもとづく同一性理論こそが必要なのだと説く。この批判を踏まえ、シェリングは『わが哲学体系の叙述』において、バルディリの純粋に論理的な同一性理論を非難した上で、主客対立の「絶対的無差別」を捉える同一哲学の立場を明確に打ちだす。が、この構想はラインホルト(『寄稿』)のさらなる批判を招き、シェリングのポテンツ論や+-を用いた論理学の用法は結局バルディリの学説を利用したにすぎないと指摘されてしまう。
ヘーゲルは『差異論文』で、「同一性と非同一性の同一性」という独自の表現を駆使してシェリングの同一性概念を補完しようと試みた。しかし栗原氏が強調するように、ヘーゲルは他方で、シェリングの同一性を「連続性(Kontinuität)」としても表現したことで、同一哲学の限界を示してしまっている。そしてヘーゲル自身はその後、シェリングの図式な同一性モデルを脱却し、むしろバルディリやラインホルトの哲学から「意識の自己超出モデル」を批判的に摂取することで、自らが提示した「同一性と非同一性の同一性」を独自に「無限性」として捉え直してゆくことになった。
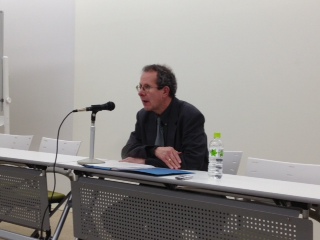 ヤメ氏は、ヘーゲルが初期の神学論でユダヤ教精神を規定するさいに使った「想像にとっての真理」という表現を取りあげ、そこにヘルダーとの接点・影響・差異を読み込む比較研究をおこなった。ヘーゲルによるヘルダーへの言及は全著作を通じて少ないが、ヤメ氏はヘルダーの『人類最古の記録』、『ヘブライ文学の精神』、『神学の研究に関する書簡』を詳細に読み解きながら、モーセの立法(Gesetzgebung)についての解釈やユダヤ教精神の帰趨をめぐる論点に、初期ヘーゲルとの確かな共通項を見出してゆく。
ヤメ氏は、ヘーゲルが初期の神学論でユダヤ教精神を規定するさいに使った「想像にとっての真理」という表現を取りあげ、そこにヘルダーとの接点・影響・差異を読み込む比較研究をおこなった。ヘーゲルによるヘルダーへの言及は全著作を通じて少ないが、ヤメ氏はヘルダーの『人類最古の記録』、『ヘブライ文学の精神』、『神学の研究に関する書簡』を詳細に読み解きながら、モーセの立法(Gesetzgebung)についての解釈やユダヤ教精神の帰趨をめぐる論点に、初期ヘーゲルとの確かな共通項を見出してゆく。シュトゥルム・ウント・ドラングの思想家ヘルダーは、旧約世界の歴史叙述に疑念を差し挟む啓蒙主義や、古代ギリシア・ローマに理性的人間の範型を求める古典主義の(近代的価値観に依拠した)一方的な歴史観に異を唱えた。他方で彼はモーセ解釈などを通じ、旧約世界の描く奇蹟や立法は、決して不合理なものではなく、「人類の幼年期」なりの仕方で自然的・直観的に語られた体験、すなわち「合目的に選り抜かれた美」の表象として受けとめられねばならないと説く。ヘルダーの歴史主義は、歴史全体を「自然なグラデーション」と見なすものであり、古代ユダヤ教の精神を享受しようと思えば、何よりその時代の精神や物語の精神に「身をおいて」みることが求められる。ユダヤ教の評価をめぐっては、ヘルダーがキリスト教との連続性を、ヘーゲルが両者の断絶を強調している点で違いはあるが、それにもかかわらずヘーゲルがユダヤ教精神に認めた「想像にとっての真理」と言われるものは、以上のようなヘルダーの歴史主義に深く根ざしているのだとヤメ氏は述べる。
今回ヤメ氏が参照したヘルダーの文献は、どれも日本で取り上げられることがまだ少ないため、内容そのものが貴重だった。初期ヘーゲルとヘルダーの思想的つながりを深く理解するためにも今後欠かせない資料となるだろう。



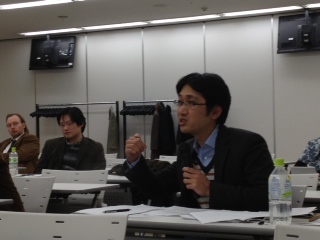
三氏の報告をめぐっては活発な質疑応答が交わされ、議論が尽きなかった。たとえば、フランク氏と栗原氏に対しては、両氏の理解するシェリングの同一性概念は同じなのか異なるのか、といった(まさに当シンポジウムのタイトルにも関わりそうな)質問が寄せられた。ヤメ氏に対しては、『ドイツ憲法論』や『キリスト教の精神とその運命』など他の論稿の内容に照らしながら、ヘーゲルのヘルダー評価がもつ射程や意義に関する質問がなされた。
[文責=阿部ふく子(日本学術振興会特別研究員)]