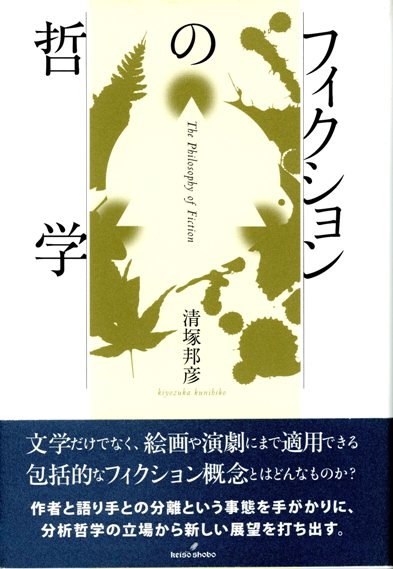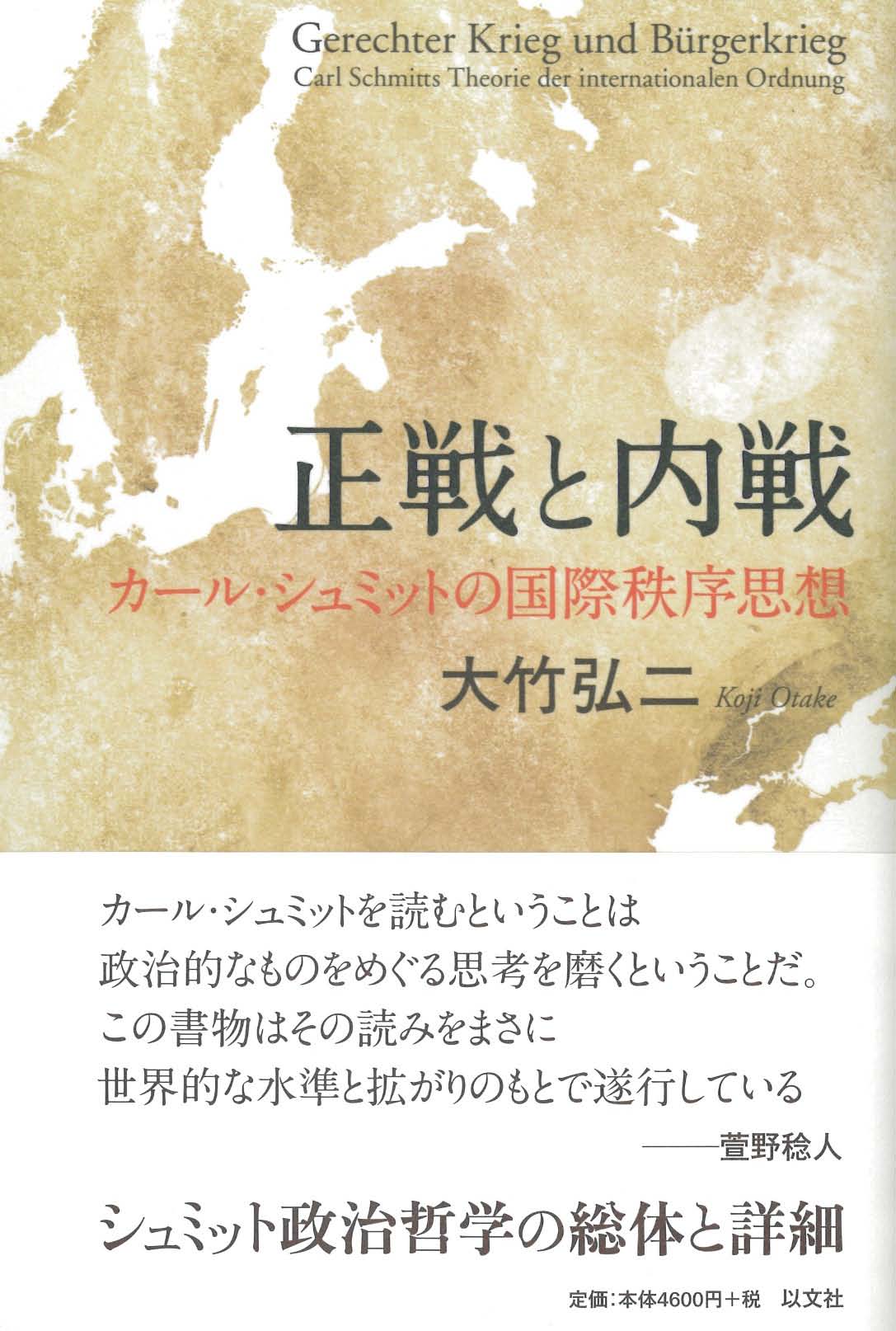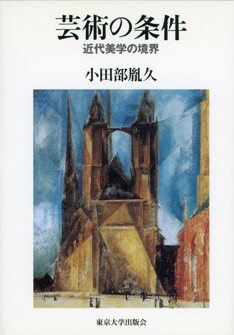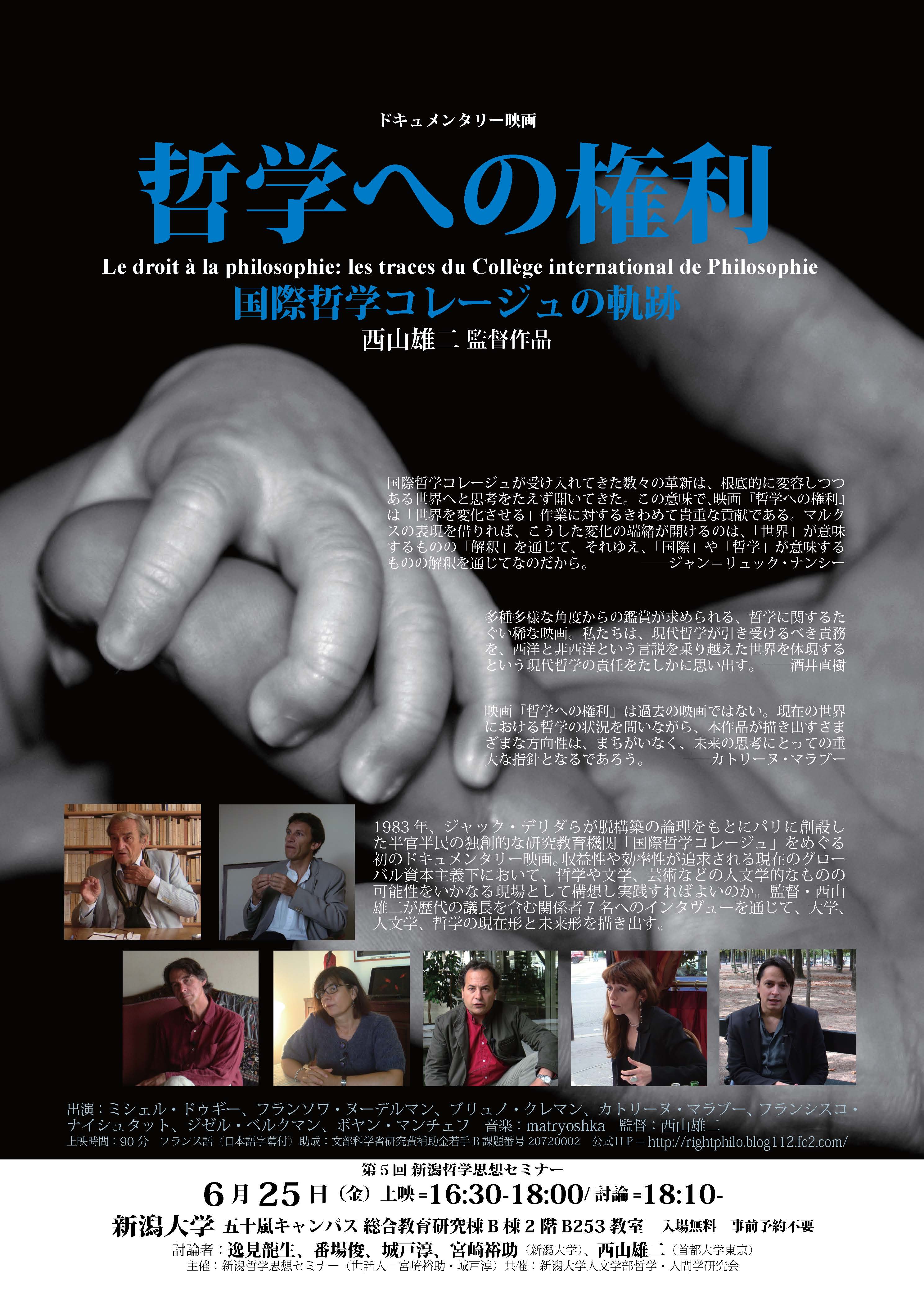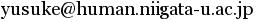第9回新潟哲学思想セミナーが開催されました 【NiiPhiS】

第9回セミナーでは、講師に関西大学の門林岳史先生をお迎えして、「メディアの消滅──マクルーハンからポストメディアへ」というテーマのもと、私たちの生活において欠かせない情報伝達の、あるいは情報収集の手段(後に、このセミナーによってメディアはたんなる情報伝達の手段ではなくメッセージそのものであるということが理解できたのだが)であるメディアの概念について、そしてそのメディアの行方について詳細にお話していただきました。
 門林先生はこのセミナーを通して、現代社会においても、どの時代のどのような社会においても、必要不可欠な概念であるメディアについて再び考えなおし、メディア以降のメディア、ポストメディアの可能性について深く考える契機を私たちに与えて下さいました。会場は多くの学生や教員によって埋め尽くされ、予定の時間ぎりぎりまで議論が盛り上がり、たくさんの質疑応答が投げ交わされました。
門林先生はこのセミナーを通して、現代社会においても、どの時代のどのような社会においても、必要不可欠な概念であるメディアについて再び考えなおし、メディア以降のメディア、ポストメディアの可能性について深く考える契機を私たちに与えて下さいました。会場は多くの学生や教員によって埋め尽くされ、予定の時間ぎりぎりまで議論が盛り上がり、たくさんの質疑応答が投げ交わされました。 コメンテーターとして、新潟大学の石田美紀先生にもお越しいただき、門林先生に対峙するという形で発表していただきました。門林先生も石田先生も上手くメディアを使いこなしながら、画像などを見せてわかりやすく、具体的に発表されていました。私も人間学ブログというメディアを用いて、両先生方の発表をそっくりそのまま報告したいと思っているのですが、私の力量にも字数にも制限(=限界)があるので、全体の議論からできるだけ逸れることなく、個人的に興味深かった箇所を重点に、今回のセミナーの内容について紹介させていただきます。
コメンテーターとして、新潟大学の石田美紀先生にもお越しいただき、門林先生に対峙するという形で発表していただきました。門林先生も石田先生も上手くメディアを使いこなしながら、画像などを見せてわかりやすく、具体的に発表されていました。私も人間学ブログというメディアを用いて、両先生方の発表をそっくりそのまま報告したいと思っているのですが、私の力量にも字数にも制限(=限界)があるので、全体の議論からできるだけ逸れることなく、個人的に興味深かった箇所を重点に、今回のセミナーの内容について紹介させていただきます。